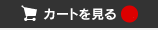2015年8月17日
2015年11月2日
第四回 ゴジラ俳優 中島春雄氏(後編)
――ちょっと話は飛びまして、シリーズ第6作『怪獣大戦争』(65年)でのゴジラのシェーについて。
中島
これはオヤジさん自身のアイデアで、「撮影しても完成作品に使うかどうか分からないが…」と言われたけれども、「いいですよ、やりましょう」と答えてね。着ぐるみが宙吊りになる演技は、『フランケンシュタイン対地底怪獣』(65年)でバラゴンを吊ったテクニックの応用なんだよね。この頃の着ぐるみは素材の良さや作り方の進歩もあって、本当に自在に動けたんだよね。だから難無くこなして楽しかったよ。
――シリーズ第7作の『南海の大決闘』(66年)から、カメラマンだった有川さんが特技監督になられました。
中島
有川さんはカメラマンの時は、いつ腹這いの姿勢になっても良いように、常に座布団を持っていてね。この作品の頃は円谷さんもテレビなんかで忙しくて、タイトル上では特技監督はオヤジさんだったけれども、実質、現場を仕切ったのは有川さんだったね。テキパキとした仕事振りだったけれども、ちょっと彼の演出は素っ気無い感じがしたね。
――この時の新怪獣エビラとの戦いは、水中での撮影もありましたね。
中島
第一作『ゴジラ』の時も水中で撮影の待機をした話をしたけれども、僕はアクアラングの免許も持っていたので、水中での撮影も何なくこなしたよ。水絡みの撮影は、たいていスケジュールの最後のほうだったけれども、着ぐるみで潜れば当然水を吸って重たくなっちゃて、撮影後にはランプで温めるんだけれども、なかなか内部が乾かなくてチョーさんなんかは徹夜をして大変だったようだよ。
――シリーズ第8作の『ゴジラの息子』(67年)では、大仲清冶さんがゴジラを演じました。
中島
オヤジさんから「この作品では、ゴジラ親子の身長差をハッキリと出さなければならないから」と言われて、大柄で身長が180センチもある後輩の大仲君がゴジラを演じることになってね。着ぐるみも彼に合わせて新調されたけれども、撮影中の昼休みに指を怪我して降板してね。急遽、代わりに関田(裕)君が演じたけれども、自分の体形に合わせた着ぐるみじゃなかったので、けっこう苦労してたね。この時のゴジラの顔は縦に長い感じに仕上げられていて、あまり僕の好みではなかったね。
――関田さんは着ぐるみ役者としていかがだったですか?
中島
テッチャンや広瀬さんをはじめとして、いろんな役者に殺陣をつけて、数多くの立ち回りをやったけれども、一番良かったのは関田君だね。彼はこちらの思いをよく汲みとって合わせてくれて、エビラやサンダ、メカニコングを上手に演じてくれたね。実は着ぐるみ役者を決めるのはオヤジさんで、演技がダメだと本人には何も言わないで、その代わり二度と使わないんだよ。その点、関田君は5〜6作品に起用されたから、演技をきちんと認められていたんだね。
――ミニラ役の小人のマーチャンは深沢政雄さんですね。
中島
深沢さんは誰が見つけてきたのかは知らないけれども、海外の演芸団に呼ばれたり、国内では舞台やキャバレーでコントをやっていたベテランの芸人さんだった。ミニラの着ぐるみは薄くて軽いものだったけれども、彼もけっこうな歳だったからね。でも、劇中のミニラのよちよちした愛嬌のある歩きなんかは自分で考えたもので、傍から見ていても真剣に取り組んでいたね。
――有川さんは生前、『ゴジラの息子』で中島さんは未出演だったと回想されていましたが…。
中島
いやいや、それは有川さんの記憶違いだね。オープニングやタイトルバックの海上でのシーンは、以前のゴジラの着ぐるみを使っているから、間違いなく僕が演じているよ。
――その後、円谷さんが体調を崩されたさ中に、ゴジラ映画の第10作『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』(69年)が公開されました。
中島
これは本編と特撮が別々に仕事をしないで、一班編成で製作した低予算の作品だね。監督の本多さんは特撮のことは何も分からないので、いろいろな相談を受けたけれども、可能な限りのアドバイスと合わせて、新怪獣ガバラが登場する特撮部分の演技指導をしたよ。
――昭和45年の1月には、特撮班の中心であった円谷英二さんが逝去されました。
中島
オヤジさんが亡くなったのを聞いた時は、あまりにも突然のことだったので本当にショックでね。これで伝統ある東宝の特撮班も解散して、ゴジラ映画もお終いだと思ってたね。生前のオヤジさんは、「『竹取物語』や『ニッポン・ヒコーキ野郎』を撮りたいんだよなぁ」と言っていたけれど、どちらも怪獣が出ないんじゃ、自分の出番は無いなとがっかりしたね(苦笑)。
――円谷さんの死去をきっかけにか、その後、長年続いていた東宝の俳優制度は廃止されてしまいました。
中島
その頃に「東宝の俳優がみんなクビになる」との噂が撮影所内に流れてね。所属俳優の一部は日活に行けば一期生になれると、6〜7人が日活の撮影所に行ったけれども、結局ご破算になってね。テレビの影響が大きくなって映画界も斜陽の時を迎えて、邦画の各社共に存続が危ぶまれたんだね。まぁ実際に大映は倒産して、日活はロマンポルノの映画会社になったからね。
――そんな状況の中でもゴジラ映画は作り続けられ、シリーズの第11作『ゴジラ対ヘドラ』(71年)は、公害怪獣のヘドラが新しい敵怪獣として登場しましたね。
中島
ヘドラのことを僕ら現場のスタッフは“ゴミ”って呼んでいたんだけれども(笑)、最終形態のヘドラは重さが100キロ以上もあって、自分の力ではろくに動けないから、結局、撮影ではゴジラが一人相撲をしなくてはならなくてね。これは3本の長い首の操演が大変なキングギドラも一緒でね。こういう時は、とにかく自分のゴジラが細かく動き回って、動けない敵怪獣を画面上でフォローしたよ。
――特撮監督には、中野昭慶さんが昇格されました。
中島
中野さんは『キングコング対ゴジラ』の頃から、円谷組の助監督としてスタッフの一員になったんだね。この時は本編の坂野(義光)監督のサポートをしつつ、一斑体制の低予算の中でも懸命に撮影をこなしていたね。中野さんといえば、昭和時代の当時を知る役者やスタッフがけっこう死んでしまって、今では昔のことを率直に語り合える良い飲み友だちの一人だよ。
――『ゴジラ対ヘドラ』や次作の『ゴジラ対ガイガン』(72年)では、ゴジラはこれまでに無い激闘を繰り広げますね。
中島
この頃からだね。敵怪獣との戦いで、ゴジラが頭部や指先を溶かされたり、赤い血を噴出するようになったのは。オヤジさんだったらそんな演出はやらなかっただろうけれども、特撮担当の中野さんに言わせれば、出血の是非に関してはずいぶん上層部とやりあったとのことで、これらの描写も時代の流れということなんだろうね。
――ヘドラやガイガン役は、後のゴジラ役者である薩摩剣八郎さんこと、中山剣吾さんが演じられました。
中島
中山君といえば、「なかなか動ける若いのが来たな」というのが僕の第一印象だね。ヘドラではとにかく動けなくて苦労していたようだけれども、ガイガンの時は立ち回りがしやすい怪獣に造形されていたので、それだけでも救われたよ。でも中山君が以後、ゴジラ俳優になるとは夢にも思っていなかったよね。まぁ、新しくゴジラを演じる役者さんは、僕のモノマネでは無くて、きちんと自分ならではのオリジナリティを出してやってもらいたいなと思うね。
――中島さんにとって、『ゴジラ対ガイガン』がゴジラ役の最終作になりましたね。
中島
実際に『ゴジラ対ガイガン』が、僕がゴジラを演じた最後の作品になるんだけれども、その時の自分にはそんな意識はちっとも無かったね。『ゴジラ対ガイガン』の直後に仕事場がボウリング場に変わったけれども、自分の年齢もこの時43歳で、まだまだ50歳まではゴジラ役をやれればと思っていたからね。だからゴジラ役は自然消滅なんだよ。
――そうだったんですか、それは今まで存じませんでした。それでは、ボウリング場に移られたその経緯をお聞きかせ下さい。
中島
上層部の課長から「俳優をクビになっても、東宝には子会社がありますから、ボーリング場やゴルフ場に残りたい方はそちらに行って下さい」と言われてね。仕事が無くなるのも困るから、だったら行ってみようと思って。それで新宿のコマ劇場の隣りにあるボウリング場に研修に行ったけれども、実際に働いたボウリング場は、向ヶ丘と成城だったよ。東宝の子会社にいれば、また撮影所からゴジラ役のお呼びがかかるんじゃないかとの期待もあったけれども、結局、僕抜きで『ゴジラ対メガロ』(73年)以降のゴジラ映画が作り続けられたね。そういえばこの頃には、劇場版の『日本沈没』(73年)で、丹波哲郎さん演じる首相の運転手役を演じたこともあったけれども、今思えばこれが役者としての最後の作品になったんだね。
――映画の撮影以外に、テレビやイベントに怪獣役で出演されたことと思いますが、その時のエピソードがございましたら…。
中島
本当にいろんな番組に出演したけれども、『おはよう!こどもショー』(65年〜)にゴジラの着ぐるみを登場させたこともあって、その際にロバくん役の愛川欽也にスタジオで会ったら、「先輩、おはようございます!」っていきなり言うから、「俺はお前の先輩じゃないよ!」って言ったら向こうは押し黙っちゃってね。初対面なのに、ちょっと調子が良い奴だな〜と思ったね。
――ゴジラ以外で演じた東宝怪獣で、特に印象深いもの何ですか?
中島
ラドンやモゲラ、バランやバラゴンとたくさんあるけれども、やっぱりそれは『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』(66年)のガイラかな。着ぐるみもゴジラに比べたら、たいへん軽く作ってあるので、立ち回りもしやすく動きやすく爽快だったね。確か自分の顔を直接型取りして作った怪獣の着ぐるみは、このガイラだけだったと思うよ。それから、ゴジラなんかの怪獣は人間の動きに見えてはダメだと言われたけれども、このガイラやサンダは、逆に人間らしい動きで怪獣じみた動きは一切しなかったよ。だから関田君が演じるサンダとの対決は、思い切りプロレスの感覚で演じたね。
――ガイラの着ぐるみ役では、テレビの『太陽のあいつ』(67年)にも出演されましたね。
中島
あぁ、これは懐かしいね。映画の舞台裏を見せ場にした、東宝テレビ部製作のドラマだね。自分が出演したのは第2話「怪獣をぶっとばせ!」の回で、演技が上手ではない怪獣役者・田辺役を演じたんだね。怪獣演技に関してはベテランだった自分に、わざと下手な怪獣芝居をさせるところがミソで、劇中では円谷プロの怪獣・キーラとガイラの対決があったね。でも、自分の顔がハッキリ写って、しかもセリフが多い役だったので、けっこうやりがいはあったよ。
――中島さんは怪獣役以外に、東宝の映画に数多く出演されましたが、印象深い監督、印象深い作品をお聞かせ下さい。
中島
う〜ん、数が多いからあまり絞れないけれども、俳優学校の時代に出演した、黒澤明監督の『野良犬』(49年)は忘れられないね。大泉の撮影所での徹夜の撮影で二つのシーンに出演したんだけれども、完成作品を見たら自分の出演シーンが全部カットされていてね(苦笑)。あの時はちょっとショックだったね。その後の黒澤監督の代表作の『七人の侍』(54年)の時には、箱根ロケの際に僕の顔を見た黒澤監督が「お前、昔見たなぁ」と言われて。この作品では野武士の役を演じたけれども、黒澤監督から「時代劇の芝居をするな」と指導されて意味が分からず困ったね。これは時代劇も自然に演じろとの意味で、東映の時代劇調の演技をするなとの言葉だったんだね。この時、黒澤監督には撮影後にジョニ赤のウイスキーも皆で一緒にご馳走になってね。良い思い出になったよ。
――特撮映画でも、本編の随所に出演されていますね。
中島
これは監督の本多さんが気を効かしてくれて、特撮の撮影で待ち時間が長い時を見計らって、本編の撮影に呼んでくれたんだね。セリフは無くても目立つ処に立たせてくれて、良い気分転換にもなったね。
――平成22年には、洋泉社さんから中島さんの映画人生を網羅した「怪獣人生」が出版され、改めて中島さんに注目が集まりましたね。
中島
それはそうなんだけどね。でも、当初はこの本について断っていたんだよ。何より円谷のオヤジさんの本もちゃんと出ていないのに、自分の本を先に出すわけにはいかなくてね。結局、何度も打診を受けてこちらが根負けしてね。長時間のインタビューを受けて、それで出版されることになったんだよ。自分がゴジラや他の怪獣に対して、如何に考え如何に演じていたか、その思いのたけを全てぶつけたよ。
――中島さんの近況をお願いします。
中島
これまでにもアメリカの各地をはじめとして、海外のいろんなところに特撮イベントのゲストとして行ったんだけれども、今年は4月にボストン、5月にダラスに行って、7月末にはフィアデルフィア、10月にはニューヨークに行く予定でね。最近では、ようやく長時間の移動の飛行機にも慣れてね。海外のイベントでは何万人という単位でファンが集まるので、その熱気だけでも大変なもので、サインをするのも本当に一苦労だよ(笑)。
――長年、ゴジラを演じた事について振り返られて思う事とは?
中島
第一作の『ゴジラ』から『ゴジラ対ガイガン』まで、12作品でゴジラ役を演じられたことは、何より自分にとっての勲章だね。着ぐるみでの撮影の際には、どんな形で地面に倒れようとも、直ぐさま起き上がれる演技が出来たことは、ゴジラ俳優としての誇りと自負があったよ。やっぱり戦時中に海軍でみっちり鍛えられたことが、どんなに苦しい状況でも乗り越えられる原動力になっているのは間違いないね。
――最後に本インタビューのテーマ「俺とゴジラ」についてお願いします。
中島
自分が演じたゴジラがこんなに有名になって、世界を代表するムービーモンスターになろうとは、もちろん夢にも思っていなかったよ。手探りだった第一作から、自分が一生懸命にゴジラを演じた甲斐が何よりあったよね。最近ではハリウッドの市長にも歓迎されたけれども、もしも俳優の仕事のみを続けてやっていたら、きっとこんなことはおそらく無かっただろうから、自分にとって怪獣ゴジラは切っても切れない存在になったね。まさしくゴジラ様々だよ(苦笑)。
――本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。
取材&インタビュー構成:中村 哲(特撮ライター)