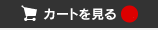2018年2月9日
2018年2月2日
第六回 監督 大河原孝夫氏(前編)
担当された4作品のゴジラ映画をお話の中心に助監督時代の東宝特撮作品のエピソードをお聞きしました。
――東宝への入社が73年の大学卒業後とありますが、資料によりますと、別セクションの採用で入社とありますね。

大河原
別セクションというか、東宝は本社のデスクワークで採用したつもりなんですよ。
撮影所は合理化を進めてる最中だったので、撮影所志望の新入社員は認めないとの状況でね。
とはいえ、どうしても現場に行きたいとの気持ちが強かったので、人事部にアピールしたり、企画書やシノプシスを書いたりして…。
それで、当時副社長の藤本真澄さんだったかな。
口添えをしてもらって、二人ぐらいならいいんじゃないかという事で、自分と『モスラ2 海底の大決戦』(97年)を担当した三好(邦夫)君と二人で出向という形で撮影所に行かせてもらいました。
――助監督として就かれた一番初めの作品が、特撮大作の『日本沈没』(73年)ですね。
大河原
これはたまたまです。
助監督の先輩にお前はこれをやれって言われて、『日本沈没』の準備に参加したという。
でも、右も左も分からなくて、オーストラリア大使館の取材や図書館に行っての資料調べ、そして現場をこなすのに精一杯でしたが、カチンコを打つ練習だけは毎日やってたかな。
今思えば、本編の演出部の数も多くて、普通は3人くらいなのに6人いましたからね。
そういえばこの時に自分が就いた、本編B班のカメラマンは木村大作さんで、遊撃班みたいな感じでやっていましたね。
――監督の森谷司郎さんのご印象は?
大河原
地方ロケが終わって、宿屋で寝っ転がっていたら、森谷さんから「お前はカチンコ打ってるだけじゃねえか」と言われた記憶があります。
何より森谷さんは、黒澤(明)監督の右腕として長いことやってましたから、あまり気軽に話せる存在ではありませんでしたね。
――撮影時のエピソードを。
大河原
後半は逃げ惑う群集のモブシーンばかりで、それが大変だったですね。
当時、美術の村木(与四郎)さんがオープンセットを建てて、火を点けて燃やして倒したりしてね、一つ間違うと怪我人が出るような撮影だったんですが、カチンコを打たずに、決まったタイミングで飛び出すグループの先頭に配置されたりしてね。
ですから、必死で走って逃げ回りましたよ(苦笑)。
連日、エキストラと一緒に、埃だ、火だ、水だ、雨だ、ガラスの破片はぶっかけられるし。
その内にエキストラの皆さんも学習しまして、帽子を被る人がやたら増えましてね。
本番前に「みんな帽子を被っているじゃないか!」と、森谷監督に怒られました(笑)。
――大規模に特撮を駆使した作品ですが、特撮絡みのご記憶は?
大河原
特技監督の中野昭慶さんが撮影したラッシュを見て、あまり森谷さんのイメージに合わなくて、何か所か注文をしていたようです。
最終的には、火山の噴火の実写映像とかも効果的に使って、一本の娯楽映画として見事に仕上がりましたね。
――『日本沈没』の後の特撮作品ですが、『ノストラダムスの大予言』(74年)、『大空のサムライ』(76年)、『連合艦隊』(81年)と担当されました。
大河原
特撮ものもいろいろとやったね。
『ノストラダムスの大予言』は監督が舛田(利雄)さんだったけれども、あけっぴろげな性格で、どんな球でも器用に打つ人なんだなあっていう気がしたね。
僕は黒澤監督の影響もあって、シナリオが何より大事だと考えていたんだけれども、最初にシナリオを読んで、「ほんとにこんなホンでやるんですか?」って先輩助監督に言ったら、「ホンのことは何も言うな!」と釘を刺されたね(苦笑)。
――主演の丹波哲郎さんの熱演が凄かったですね。
大河原
丹波さんは『日本沈没』に続いてだったけれども、なんかこう自分とはウマが合って、現場ではけっこう可愛がってもらいました。
――撃墜王の坂井三郎を主人公にした『大空のサムライ』は、初の戦記映画ですね。
大河原
自衛隊の鹿屋基地だったかな? 結構長いこと地方ロケに行って、これは川北(紘一)さんの特技監督のデビュー作だったね。
負傷した坂井が操縦する帰投中の零戦が反転するカットが印象的でね。
これはフロントプロジェクションで処理したのだったかな? ダビングが終わって作品が完成したと思っていたら、チーフ助監督の井上(英之)さんから電話があって「撮り足しをする」って。
それが、俳優の勝部義夫さんが坂井三郎さんにインタビューするオープニングのシーンで、そこのセリフを考えろっていうので自分が全部書いたんだよ。
「彼らこそ、本当の大空のサムライじゃないでしょうか」とかね。
――そうですか、あのオープニングのセリフは大河原監督が書かれたものだったんですね。
大河原
まあ、井上さんも少しでも自分に勉強しろという意味でやらせたのかもしれないけれども、何より『日本沈没』からの付き合いなんで、もちろん逆らえないからね(笑)。
――引き続き、戦記大作の『連合艦隊』について。
大河原
この作品は、プロデューサーの田中友幸さんも特に力が入っていて、松林(宗恵)監督の代表作でもあるし、東宝戦記映画の集大成作にもなったんだね。
――松林監督は、どんなタイプの方だったですか?
大河原
松林監督は自分で言っていましたけれど、嵐が来るとじっと伏せていて、「過ぎ去るのを待つのがいい」と言うタイプでしたね。
自ら向かっていくという事はやらない人で。
この作品では、森繁さんにセットで「今日、残業になっちゃうけど、いいかな?」、「なにぃ〜!?」とか言われちゃって。
監督がだよ!?(笑)
――お二人の微妙なパワーバランスが分かりますね。
大河原
まあ長い付き合いなんだろうね。
森繁さんも「本番もう一回やんのか? 黒澤組みたいになっちゃうぞ」って。
あんまりリハーサルで固める的な事には賛成されない俳優さんで、何回も同じ演技をやるのは抵抗あるタイプなんでしょうね。
――ラストの戦艦大和の爆沈は、名シーンですね。
大河原
谷村新司さんの『群青』のエンド主題歌とも相まって、良いシーンに仕上がったよね。
大和沈没までのシークエンスでは、財津一郎さんが灼熱のバルブを開けるシーンや、甲板での着弾の演技とか、後半の撮影ではそんなシーンばかりで、それはそれで大変だったね。
――84年版の『ゴジラ』で、初めてゴジラ映画に関わりますが、この作品でチーフ助監督に昇進されました。
大河原
『ゴジラ』は、プロデューサーの田中友幸さんがいろいろ頑張って、あそこまで半ばキャンペーンじゃないんでしょうけど、ファンの皆さんの後押しもあって実現した企画でしたね。
監督は橋本幸治さんでしたが、橋本さんは性格からか、真面目で手堅く撮ろうとされる監督さんでね。
それはそれで成功する作品もあるんだろうけど、自分なんかはどっちというと、やっぱり緩急っていうか、どこかで肩の力を抜いてっていうような事が、ある意味映画のストーリーに必要なのかなと思ってますね。
それから、田中友幸さんの話になるけれども、セットで閣議のシーンの撮影中にやって来られて、橋本監督の指示で、出演者が重々しい感じでセリフを言ってたんだけど、「それじゃダメだよ、もっとテンポあげてやんなさい」ってアドバイスをされて。
次のテストではもう掛け合いみたいになって、「あ、こっちの方がテンポが良いなあ」って。
田中さんの若い頃は存じ上げないけれども、なかなか現場や映画の事が分かっている方なんだなと感じましたね。
――メインスタッフによるシナリオのチェックでも、田中さんがアドバイスされたようですね。
大河原
ええ。
準備期間にシナリオの各シーンのチェックを冒頭からやっていて、シーン10くらいで引っ掛かったんですね。
協力製作の田中文雄さんは全部の話を進めたいから「そこは後で直すとして進みましょう」って言うんだけど、田中さんは「イヤ、ダメだ!」と言われて、一切譲らなかったね。
ペンディングにしないで、きちんと目の前の問題を解決してから進みなさいという、これは見習うべきだなと思った。
田中さんのそういうところは、どっちかというと自分なんかと波長が合うタイプでしたね。
皆で知恵を出しあって少しでも作品を面白くしようとの、その基本的な姿勢も良かったですね。
――特に苦労された撮影は?

大河原
実物大に再現したゴジラの足が、地面に降って来るのも本編班の撮影でね。
クレーンを3台くらい使って、一回こっきりの撮影だったので、クレーンのタイミングを合わせるのが大変でしたね。
でも、いろいろと僕にとっても、それだけ思い入れのある作品になりました。
――本作の予告編は、川北さんが作られたとの事ですね。
大河原
そうです、自分がサポートに付いてね。
これは川北さんが「是非ともやらせて欲しい」って手を上げたんだと思いますよ。
それで、川北さんがその予告編にゴジラの口に泡が付いてるカットを使ったんですけども、当時の感覚で言うと、「新鮮ではあるけれども余りにも生々しい」と反対する人がいて。
でも、そこは川北さんが押し切って「何言ってんだよ、あれが良いんだよ!」って言い切ってましたね(笑)。
――初めてゴジラ映画にタッチしたわけですが、後年4作品も関わる事になりますが、この時はまさかそんなことになろうとは…。
大河原
それはもちろんね。
助監督は順番で作品を担当する事になっていたんだけど、ゴジラ映画も、もちろんやりたくなかったわけでは無いけれども。
とはいえ、大のゴジラマニアとして知られる手塚(昌明)君ほどではなかったけどね(笑)。
――今回のインタビューに当たって、大河原監督の助監督時代の担当作品を、東宝映画の作品データを当たって調べていましたら、作品数が多くて、助監督の経験が結構長かったんだなというのが伺えました。
大河原
そうなんだよ。
若いのというか、自分達の下のスタッフが、全然撮影所に入って来ないんだもん。
だから、いつまでも若手として扱われたね(苦笑)。
――幾多の監督さんの助手に就いてのご感想を。
大河原
さっき話をした森谷司郎さんや舛田利雄さんをはじめとして、『青春の門』(75〜77年)の浦山(桐郎)さんや『あ・うん』(89年)の降旗(康男)さんにしろ、まあ、やっぱりそれぞれ監督としての持ち味が違うというのかな…。
でも、どの監督さんにしても、何としても作品を面白くしようと思ってやってることに間違いはないんでね。
それから、監督と助監督との関係でいえば、現場であからさまに教えてくれる人はめったに無かったね。
でも、浦山さんは、けっこう「こうした方がいいよ」みたいな感じでアドバイスをしてくれました。
――映画を面白くするためには、何が必要だと?
大河原
それはやっぱり、シナリオですね。
ホンが面白かったら、多少腕の鈍い人でもそれなりのものには仕上がるだろうし…。
本当につまらないホンだと、いくら力量がある監督さんがやっても、難しいっていうのはけっこう感じますね。
――この後にご自分が監督する作品については、納得されたシナリオでやられたという事ですね。
大河原
作品を作る以上は、やっぱりお客さんに喜んでもらわないと話にならないわけでね。
ですから、まずは良いシナリオを仕上げるというのは、常に自分の映画製作のベースとしてありました。
――その後、自ら執筆された脚本で第13回城戸賞を受賞した、超能力バトルをテーマにした『超少女REIKO』(91年)で、映画監督のデビューを果たされました。
大河原
大作のシナリオを書いても、新人の一本目から5億も6億もかかる企画が通るわけはないと思っていましたからね。
ローバジェットで、中身がギュッと詰まっててという、ある意味戦略的な思いはあって、学校や病院とか、舞台をなるべく限定したドラマにするというのも考えていました。
城戸賞の準入選が87年で、映画の公開が91年。
4年もブランクがあったのは、一言で言えばなかなか主演の女優さんが見つからないという事で、毎年ラインアップには載るんだけれど実現しなかった。
それで、黒澤さんじゃないけれども、時間があったので絵コンテを頭から最後まで書いてました。
――自ら脚本を書くということは、監督が脚本の全てを熟知されているわけで、そのメリットは大きいんでしょうか?
大河原
いや、それは一概にはそう言えないと思いますよ。
例えば自分より優れた感性の持ち主の書いたシナリオで撮影する事によって、相乗作用で良いものが出せる場合もありますから。
オリジナルが必ずしもいいとは限らないと思いますね。
――主演は映画初主演の観月ありささんで、特殊効果の担当は浅田英一さんでした。
大河原
そうですね。
観月君はプロデューサーの富山(省吾)さんが見つけてきてくれました。
浅田さんとは、助監督の一本目の『日本沈没』からの付き合いですね。
特撮班を別班として立てるわけにはいかない規模の作品だったので、合成素材を中心に仕掛けを含めてアドバイザー的な立ち位置でやって頂きました。
――劇中の壁が割れるところをはじめとして、特殊効果の使い方も効果的で良かったですね。
大河原
とにかく仕掛けのあるものは、やっぱり時間がかかるんでね。
ゴジラの特撮とは違うとはいえ、特殊効果の場面では俳優さんが絡んでるんで、スケジュールの調整とかもあって苦労しました。
操演の鳴海(聡)さんは「何でも出来ますから」と言ってくれて、これはたいへん心強かったですね。
――印象に残るエピソードは?
大河原
観月君が撮影の途中で盲腸になって、結局入院されちゃってね。
チーフ助監督が頭を抱えてましたね。
主役がいないんで撮るものが無いという事になっちゃったんだけれども、なんとか皆の力を合わせて乗り切りました。
以上前編
取材&インタビュー構成:中村 哲(特撮ライター)
インタビュー原稿作成協力:mayoko