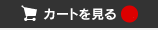2015年5月1日
2015年6月15日
第三回 特技監督 中野昭慶氏(後編)
――第15作『メカゴジラの逆襲』(75年)で、一旦ゴジラ映画は休眠の時を迎えまして、それから9年後に、特にゴジラファンの期待に応えて新作『ゴジラ』(84年)が公開されることとなります。中野監督にとっても、この作品が最後のゴジラ映画となり、これまでの技術の集大成作となりましたね。
中野
9年振りに作られたこの作品は「東宝チャンピオンまつり」の頃の作品とは違うって、かつての東宝が作っていた大作もののジャンルに入るであろう、堂々とした作品だったよ。
――作品に掛ける予算も「東宝チャンピオンまつり」の作品と比べると潤沢だったと思われますが。
中野
もちろん「東宝チャンピオンまつり」とは比べ物にならない程の予算ではあったけれども、決して潤沢ということでは無かったよ。撮りたかったけれども撮れなかったカットも多くてね。もっと密度の濃い特撮シーンを表現したかったよ。
――この復活作は、たいへんな試行錯誤の末に誕生したとのことですね。

中野
製作当初、プロデューサーの田中さんが「この作品では原点に還る」と言われて、「その原点とは何ぞや?」との、その論議を延々とやったんだよ。それで「劇中でゴジラが簡単に放射能なんかを吐いていたら、これは決して原点にはならないよ」と田中さんに言ったんだ。自分としては、核の申し子としてゴジラが現代への警鐘を打ち鳴らすというのであれば原点と言えるだろうと思っていた。だけど、広島、長崎への原爆投下やビキニ環礁での核実験で、唯一、日本は二度も放射能の洗礼を受けて、核の恐ろしさが身近な存在であった第一作『ゴジラ』の頃や米ソ冷戦の時とは違って、この作品を製作した当時では、繁栄を享受していた日本国民にとって核や放射能の怖さはまったく現実的なものでは無くなっていてね。そういう世情の中で、如何に核や放射能の恐怖を伝えるかというところで、スタッフの皆が作品作りに大変悩んだね。
――中野監督はゴジラを生物として割り切って設定されたとのことですね。
中野
田中プロデューサーの言う「原点に還る」との発想から言えば、ゴジラは“神”とも言える存在に設定出来ないこともなくて、協力製作の田中文雄君も「“神”にすれば万能で何でもアリで楽じゃないか」とも言っていたけれども、そうなっちゃうと対する人間は何も打つ手が無くなってしまう。このジレンマには脚本の永原秀一君も本当に困っちゃって、最終的には生物とは口に出さないまでも、それを設定したドラマを構築したんだよ。
――劇中での代表的なゴジラの生物的な描写といいますと、帰巣本能のシーンでしょうか。
中野
そうそう。ゴジラ自体に帰巣本能の設定がないと、ラストで大島の三原山に誘導出来ないんだよ。“神”が勝手に三原山に行ってくれましたでは、どうあってもお話が成立しないからね。
――先程、如何に核や放射能の恐怖をどう伝えるかとのお話がありましたが、それを劇中でストレートに描写したのが、劇前半の井浜原発のシーンですね。
中野
そうだよ。井浜原発は、静岡県の御前崎の浜岡原発をモデルにしたんだ。炉心を取り出すシーンはゴジラの怒りであると共に、「原発はこれで良いのか!」との自分自身のお客さんへの訴えかけなんだよ。それから、この時に自分が思い出したのが、「治にいて乱を忘れず」との中国の易経の言葉で、これは平和な世にいても、万一の時の備えを怠らないとの教えでね。皆が経験した福島第一原発の件では、半世紀の時を経て、改めて核や放射能の恐ろしさを日本国民が実感させられることになったわけだね。
――それからこの作品では、第一作『ゴジラ』以来の、対戦怪獣が登場しない作品で、この部分についても腐心されたのではと思います。
中野
これもドラマ作りに於いては困ったね。敵怪獣が登場する対決ものであれば、そこからいろんな展開も望めるわけだけれども、僕もゴジラ一匹での作品作りは初めてのことだったからね。要は一人相撲をさせるしか無かったわけだけど、開き直って僕がこだわったのはゴジラのディティール。目や口、手の動きを徹底して細かく描写しようと思ったので、田中プロデューサーに「80メートルサイズの実物大のゴジラを作りましょう、こういうのが銀座の街にそびえたらさぞやカッコ良いですよ」と提案したんだ。結局それがサイボット・ゴジラになったわけだよ。
――サイボット・ゴジラの創造は、シリーズ初の試みでしたね。

中野
この作品の時に何故、サイボット・ゴジラが作れたかというと、産業用ロボット用に小指大のシリンダーが開発されて、スムーズに縦横の動きが出来るようになったんだ。自動車業界でもこの開発をきっかけに工場での自動車の組み立ての量産体制が組めたので、自動車の製造過程が劇的に変わることとなったんだよ。で、水野さん(※1) に頼んで、4メートル以上もの大きさの機械仕掛けのゴジラを作ってもらうんだけど、造形担当の安丸(信行)君もこの大きさにはびっくりしちゃってね。彼には全身の原型も作ってもらったけれども、一番の問題だったのが、撮影用のスーツとサイボットの顔が似ていないことでね。安丸君も可能な限りサイボットの製作現場に出向いて助言をしてくれたのだけれども、ちょっとどうにもならなかったね。
――サイボット・ゴジラの撮影時のエピソードはございますか?
中野
現場では、このゴジラを上下に分割して撮影をおこなったよ。これまでに表現することが出来なかった、ゴジラの下瞼(まぶた)や上唇の動きなんかも描写して、本作ならではのゴジラのディティールを追求したんだ。それからサイボット・ゴジラはコンピュータ制御なんだけれども、ステージ内は何といっても埃が多くてね。コンピュータがとにかく埃に弱くて、接点に埃が少しでも付くと、とんでもない動きを起こして故障しちゃうんだよね。だからコンピュータを制御するコンピュータが現場に欲しかったよ(笑)。それから撮影が進むに従って各部のゴムが腐食して、当初はスムーズだった動きもだんだん悪くなって行ってね。先端技術を積極的に撮影に導入したけれども、それを使いこなすには、まだまだ課題がたくさんあることが分かったよ。だから、サイボット・ゴジラは実際の撮影よりも、公開時のキャンペーンで日本中を回って多いに宣伝活動で活躍した、そっちの方のウェイトが大きいんじゃないのかな。
――先程の中野監督のお話にも出ましたが、この作品でゴジラの身長は、これまでの50メートルから80メートルに劇的に変化しました。
中野
第一作の頃だったら、銀座・和光の時計台を越える50メートルくらいでちょうど良かったんだけれども、それから30年もの時を経て、東京の街並みも大きく変化して、もっと大きくしなければゴジラの存在が引き立たないだろうとの意見を受けて、有楽町マリオンを越える80メートルになったんだよ。それに合わせてミニチュアのスケールも1/25から1/40へと変わってね。本当は100メートルにしたいとの思いもあったんだけれども、あまりにミニチュアのスケール感が無くなるのにも配慮してね。まあ世の中の発展度合いによって、ゴジラも我々作り手もいい迷惑を被ったということだね(笑)。
――ミニチュアセットの見所は、先の井浜原発を筆頭に、有楽町マリオンの周辺と新宿副都心ですね。
中野
有楽町マリオンと新宿副都心のセットは、劇中でも特に精密なミニチュアで、美術の井上泰幸さんらの腕の見せ所だったね。それで公開当時に「何でマリオンのシーンで東宝マークをよけたんですか?」ってよく訊かれたんだけど、この作品のゴジラは、決して理由が無い限り自らの意思で破壊しようとは思っていなくてね。たまたま数寄屋交差点付近を前進していてつまづいて、マリオンの一部を破壊してしまっただけでね。東宝の映画だからといって、決して東宝マークを壊さなかったわけじゃないんだよ。
――有楽町マリオンのミニチュアは、本物と同時進行で作られたとか…。
中野
これは僕も初めての経験で、マリオンのミニチュアは竹中工務店から建築図面を提供してもらって製作してね。本物にはビル下方に西武と阪急のマークが以前から付いていたんだけど、撮影の2日前に東宝マークが入ったと聞いて、撮影当日にあわてて付けてもらったんだよ。
――マリオンのシーンでは、壁面に写るゴジラの姿が素晴らしかったですね。
中野
本当?まあ、あのシーンもこだわったカットだったけどね。ミニチュアのマリオンの壁面のガラスが、正確且つ綺麗に配置されていたからこそ、あのカットが出来たわけだね。
――クライマックスの三原山も哀愁が漂っていますね。
中野
三原山の表現は難しかっただけに、愛着のあるシーンだね。三原山の火口の大きさに比してゴジラの姿は本当に小さいんだけど、可能な限りゴジラの姿を大きく見せて、その後に火口内に消えていくゴジラの哀しみを表出させようと腐心したよ。
――改めてお話を聞きしていますと、84年版の『ゴジラ』が、中野監督のゴジラ映画の代表作というか、集大成作だと思えます。
中野
84年版の『ゴジラ』は、自分が監督したゴジラ映画の中でも、最も世界観やスケールが大きく、撮影セットやスタッフの数も「チャンピオンまつり」の頃とは比べるまでもなくて。これまでに自分が培って来た技術をフルに使用したという点からも、僕にとってのゴジラ映画の集大成といったらそうなんだろうね。
でも、僕としては設定を突き詰められずに撮影に突入してしまい、それらが未消化で終わってしまったとの忸怩たる思いがあるのも事実なんだよ。
――シリーズを支えたプロデューサーの田中友幸さんについてお願いします。
中野
田中さんはただひたすら、ゴジラは俺が作ったんだとの誇りを持っていた人だったね。だから時代の流れの中で、周囲から「もうゴジラもスターじゃないね」と言われた時に、一番悲しい思いをしたのも田中さんだったと思うよ。でも、田中さんの思いも充分に分かるけれども、僕はゴジラを本当に誕生させたのはプロデューサーだった田中さんだけでは無く、早くから円谷英二の技術を認めて、東宝の上層部の中で唯一、第一作の『ゴジラ』の企画にGOサインを出した、当時の取締役製作本部長だった森岩雄さんの功績もあると思っているんだけどね。
――中野監督は、本多猪四郎、福田純、坂野義光、橋本幸治の4人の本編監督とご一緒にゴジラ映画を製作されました。それぞれの監督さんについて一言お願いします。

中野
本多さんは、とにかくあんなに真面目な人はいないと思うくらい、本当に良い人だったよ。絶対に喧嘩はしない、怒鳴らない。何かトラブルがあってもご自身で受け止めてね。奥様が「あなた、そんなにおとなしくて仕事が出来るの?」と心配したぐらいで、本多さんは「怒ったら辛いのはこっちなんだよ」と言ってらしたね。本多さんは映画の本当の素材は日常生活だからと、常に日常に目を向けていたけれども、そういう姿勢が劇中で日常世界が非日常と化してしまう特撮映画の本編監督として適任だったんだと思うよ。本多さんの葬儀の時の贈る言葉で、黒澤さんが「本多は良い人だった」と言われてね。あの一言は「あぁ、これはうまいことを言ったなぁ」と思ったよ。
一番数多くコンビを組んだ福田さんは、時代劇を得意としていた稲垣(浩)組のチーフ助監督を担当されていて、アクションものの感覚に長けた監督さんだったね。それで、ゴジラを見る顔とか、爆発に驚いた態度とか、そういう人間のリアクションをとるのがうまくてね。特に『ゴジラ対メカゴジラ』(74年)は良かったよ。福田さんを本多さんと並ぶ東宝特撮映画の本編監督に抜擢した、田中プロデューサーの選択眼は決して間違っていなかったね。
坂野さんは理論派で、けっこう思いきったことをやるんだけれども、もう一押しが欲しいというのが『ゴジラ対ヘドラ』で僕が感じたことだね。彼は東大文学部の美術史科の出身なので、美術系の造形や音楽に非常に精通していて、ゴジラ映画で初めて真鍋(理一郎)さんを起用しての、短くとも効果的な音楽の使い方は「うまいな〜」と思ったよ。
橋本君は助監督時代からの同期生で、おとなしい性格で何事もたいてい笑顔で受け止めてくれるので、84年版の『ゴジラ』でも、もの凄くやりやすかったとの記憶があるね。その代わり、「特撮でこう撮るからそのリアクションをよろしく頼むよ」と伝えても、もう一つノッてくれなかったなぁとの思いもあって…。福田さんが抜群に良かっただけに、本編サイドでリアクションを表出することの難しさを痛感したね。
――ゴジラを演じたスーツアクターについてもお聞きします。助監督時代から、もっともつきあいが長かったのは中島春雄さんですね。
中野
中島さんは第一作の『ゴジラ』からゴジラを演じていて、あれだけゴジラを演じることに関して、真面目と言うか一生懸命に取り組んだのは、唯一、彼だけだったね。俳優さんだったら自らの顔がレンズに写ってなんぼのもので、怪獣なんて役者の仕事じゃないと思うのが普通なのに、本当にプロフェッショナルに徹して怪獣役を演じてくれたのは頭が下がる思いだね。
――「東宝チャンピオンまつり」で敵怪獣を演じた薩摩剣八郎さんは、84年版の『ゴジラ』でゴジラ役を担当されました。
中野
武術や剣道の素養もあって、なおかつ体力と精神力がある人材という点では、薩摩君はベストだったね。何より彼は『ゴジラ対ヘドラ』や『ゴジラ対ガイガン』で敵怪獣を演じ、中島さんからレクチャーを受けていたから。僕としては静かな中に力のあるアクションにしようと思っていて、常に重量感溢れる彼の演技は、僕の要求によく応えてくれました。
――これまでに数多くのインタビューを受けられているわけですが、これまでに話したことの無い秘蔵のエピソードがありましたら…。
中野
う〜ん、話して無いことなんて無いんじゃない?そうだなあ…。84年版『ゴジラ』の三原山の撮影で、実は火口から立ち上る煙にフロンガスを使ったんだけど、フロンガスを熱すると塩化水素が発生して、これを吸って気を失っちゃったんだよ。それが本番の直前で「用意!」の声までは覚えているんだけど、その後に僕の「スタート!」の声が無かったのでスタッフの皆は「どうしたんだ?」と思ったらしくて。時間にしたら2〜3秒くらいらしいんだけど。ハッと正気に戻ったら「俺、何をやってんだろ?」と思ってね。ここまで危ない思いをしたのはこの時ぐらいだけど、撮影現場は危険なこともけっこう多かったね。
――ご自分が現場を離れた後の『ゴジラVSビオランテ』(89年)以降のゴジラ映画についてご感想をお聞かせ下さい。
中野
川北(紘一)君の時代はシリーズ化して、これはこれで良いんじゃないと思ったね。何よりあれだけ予算を使えて、映像自体を華やかにしているのが羨ましかった。僕と川北君のゴジラ演出で一番の違いは、ゴジラの吐く放射熱線の描写かな。僕は出来る限りゴジラが熱線を吐くのはここぞという場面に限定したけれども、川北君はけっこう派手に吐かせていて、観客へのサービス精神が旺盛だなと思ったよ。
――昨日(4月1日)、各マスコミから日本版ゴジラのメインスタッフが発表されましたが、来年に公開される新たな日本のゴジラ映画にエールをお願いします。
中野
4年前の東日本大震災を経験した日本は、改めて地震国で原発の恐ろしさを国民が認識したわけで、それらを踏まえて新作では、核や放射能、原発や自然災害の描写をどう処理するのか。もちろん主役のゴジラ自体も如何なる設定にするか。映像表現にしても最新のソフトを使い、時間と費用をかけられればハリウッドと比べて遜色の無い映像が創造出来るんじゃないかと思っているんだけれども。それらを踏まえて、29作目のゴジラ映画は「これだぞ!」と堂々と世間に公言出来る、これまでには無い新時代の日本ならではの作品を作ってもらえればと、大いなる期待を込めて公開の時を待ちたいね。
――最後に、今回のインタビューのメインテーマ「俺とゴジラ」について一言お願いします。
中野
ゴジラとの出会いは、僕の映画作りのテクニックを形成するきっかけであり、映画人生のエポックを築いた貴重な存在であったことは間違いないね。それにしても62年の『キングコング対ゴジラ』から84年版の『ゴジラ』まで、ゴジラとこんな長いつきあいになるとはもちろん夢にも思わなかったわけで、思い起こせば「僕とゴジラは、“相棒”でもあり“戦友”とも言える深い間柄であったのかなぁ」と感じているよ。
――本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。
※1:当時、マリリン・モンローなどのロボットを作っていた水野俊一氏のこと。「サイボット」はサイボーグとロボットを合わせた水野氏の造語といわれている。
取材&インタビュー構成 中村 哲(特撮ライター)